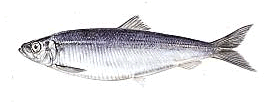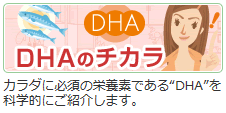【クイズの解説】一時は幻の魚とさえ言われた魚
さかなクイズ 第78問
正解と解説
【2】ニシン
ニシンは犬吠崎より北の太平洋、日本海、オホーツク海。その他、ロシア・アラスカを経てカリフォルニアに至る北太平洋、北極海に生息しています。下顎は上顎より少し長く「カドイワシ」という地方名は「角のある鰯」の意味で、分類上もイワシに非常に近縁。
ニシンには、産卵場所や生息地の異なる多くの「系群」があり、日本近海を回遊するものとしては、「北海道・サハリン系群」「石狩湾系群」「テルペニア系群」や、「厚岸湖系群」「能取湖系群」のように汽水湖に生息するものもあります。
早いものは2年で成熟。3〜4歳で産卵成熟し、北海道西岸では3〜6月に集団で接岸して産卵します。
北海道では、漁獲される時期・体色・大きさによって「春ニシン」、「夏ニシン」、「冬ニシン」に区別されます。
明治時代には桁外れの大群が押し寄せる、いわゆる「群来(くき)」現象が見られ、「春ニシン」と呼ばれる北海道・サハリン系群を中心に、年間100万トンもの水揚げがありましたが、同系群は1950年代以降すっかり姿を消し、幻の魚と呼ばれていました。
その後、1980年代に多少出現しましたが、現在も低水準が続いています。この不漁の原因としては、海洋環境の変化、乱獲、森林伐採などの説がありますが、真相はまだ判明していません。現在、日本の消費の大部分は、北米、ロシア、ヨーロッパからの輸入に頼っています。
料理
塩焼き、酢漬け、煮付け、三平汁などで賞味。ほろほろとした肉質で独特の滋味。
- 日常的には干物(丸干し、身欠きニシン)で出回っており、身欠きニシン(ミガキニシン)は、鰊蕎麦(にしんそば)や昆布巻きに使われる。
- 子持ち昆布は、ニシンが昆布に卵を産みつけたもの。
- ニシンの卵巣を塩漬けした数の子は「カドの子」が語源。正月には欠かせない縁起物。
★参考: ニシン|世界のおさかなギャラリー